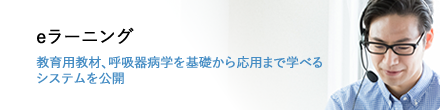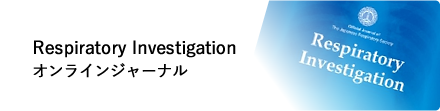呼吸器の病気
D. 間質性肺疾患
膠原病肺
こうげんびょうはい
概要
膠原病とは、本来外界からの病原体などから体を守るはずの「免疫」の働きに異常を生じて、逆に自分自身の体を攻撃してしまうことによって起こる病気の総称です。具体的な疾患名としては、多発性筋炎/皮膚筋炎、全身性硬化症(全身性強皮症)、関節リウマチ、シェーグレン症候群、混合性結合組織病、全身性エリテマトーデス、ANCA関連血管炎、結節性多発動脈炎などが膠原病に分類されます。膠原病においては、筋肉、皮膚、関節、腎臓、骨などに変化が起きますが、肺にも変化を起こすことがあります。この肺の変化が「膠原病肺」と呼ばれ、いくつかの種類があります(表1の①)。頻度が高く最も注意が必要なのは間質性肺疾患です(間質性肺疾患の一般的な説明は特発性間質性肺炎の項をご覧ください)。その他には、気道病変(気管支からの先の細い部分の炎症)、胸膜病変(肺の周りを包む膜の炎症で胸水が貯まる)、血管病変(全身の臓器の血管の炎症)などがあります。病気が現れる順番としては、肺以外に変化が起きてから肺の変化(膠原病肺)が後に出てくることもあれば、その逆もあり得ます。膠原病肺が進行すると呼吸困難(息切れ)を自覚し、治療が必要となるため、膠原病の患者さんにとって肺病変の合併の有無は非常に重要です。
症状
ごく軽度の場合は症状がないこともありますが、ある程度進行するとせきや呼吸困難(特に体を動かした時)を自覚するようになります。これらの症状は他の間質性肺疾患と同様です。肺以外の膠原病自体の症状としては、発熱、倦怠感(だるさ)、皮膚の発疹、筋力の低下、関節の痛みや腫れ、手の指先が白くなる現象(レイノー現象)などがあります。
検査・診断
膠原病に伴う肺の病変には、膠原病自体による肺の変化(膠原病肺)以外にも、感染症や薬の副作用(薬剤性肺障害)による肺の変化の可能性もあり、区別する必要があります(表1)。そのために、画像検査(胸部エックス線や胸部CT)、呼吸機能検査、血液中の酸素飽和度測定、血液検査などを行います。また、肺組織を詳しくみて確定診断する必要がある場合には、気管支鏡や胸腔鏡などの内視鏡検査や手術で肺組織の一部を採取して顕微鏡で観察する病理組織検査を行うこともあります。
治療
膠原病に伴う間質性肺疾患では、副腎皮質ステロイドとともにシクロホスファミドやアザチオプリン、タクロリムス、ミコフェノール酸モフェチルなどの免疫抑制薬が使用され、わが国ではシクロスポリンもしばしば用いられます。近年、膠原病に伴う間質性肺疾患に対する治療の指針なども出されており、自覚症状や高分解能CT所見、呼吸機能検査、病理組織パターンなどを総合的に評価し、治療方針を決定するため、主治医の先生と十分に相談してください。
(2025年10月)
| ①膠原病肺 |
|---|
| 1)間質性肺疾患 2)気道病変:細気管支炎、気管支拡張症など 3)胸膜病変:胸膜炎、胸水 4)血管病変:血管炎、肺高血圧、びまん性肺胞出血 |
| ②感染症による肺病変 |
| 細菌、抗酸菌(結核を含む)、ウイルス、真菌、ニューモシスチスなどによる感染 |
| ③薬剤性肺障害による肺病変 |
|
膠原病の治療として使用した薬剤(抗リウマチ薬など)によるもの |