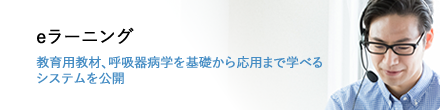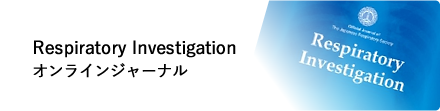呼吸器の病気
I.その他
過換気症候群
かかんきしょうこうぐん
精神的不安や極度の緊張などにより過呼吸の状態となり、血中の炭酸ガス濃度の低下が生じ、血液がアルカリ性に傾くことで様々な症状を出す状態です。神経質な人、不安症な傾向のある人、緊張しやすい人などで起きやすいとされます。
何らかの原因、たとえばパニック障害や極度の不安、緊張などで息を何回も激しく吸ったり吐いたりする状態(過呼吸状態)になると、血液中の炭酸ガス濃度が低くなり、呼吸をつかさどる神経(呼吸中枢)により呼吸が抑制され、患者さんは呼吸ができない、息苦しさ(呼吸困難)を感じます。このために余計何度も呼吸しようとします。血液がアルカリ性に傾くことで血管の収縮が起き、手足のしびれや筋肉のけいれんや収縮も起きます。患者さんは、このような症状のためにさらに不安を感じて過呼吸状態が悪くなり、その結果症状が悪化する一種の悪循環状態になります。
自覚症状
息をしにくい、息苦しい(呼吸困難)、呼吸がはやい、胸が痛い、めまいや動悸などがあります。テタニー(tetany)と呼ばれる手足のしびれや筋肉がけいれんしたり、収縮して固まる(硬直)症状がでます。手をすぼめたような形になり"助産師の手"と呼ばれます。この所見は、血圧計のマンシェットを腕に巻いて手の血流を止めるとより出やすくなります(トルーソー Trousseau徴候)。耳の前や顎の関節をたたくと顔面神経が刺激され、唇が上方にあがります(クボステック Chvostek徴候)。
呼吸がはやく、呼吸困難感を訴える患者さんで、上記の自覚症状や筋肉のけいれん、硬直などの所見があればこの病気を疑います。動脈血液ガスの検査では、炭酸ガス濃度が低く、アルカリ性になります。
治療
意識的に呼吸を遅くする、もしくは呼吸を止めることで症状は改善します。しかし、不安が強い場合には容易ではないため、まずはできるだけ安心させゆっくり呼吸するよう促すことに専念します。紙袋を口にあてていったん吐いた息を再度吸わせること(ペーパーバック法)は、血液中の炭酸ガス濃度を上昇させる効果があり頻用されていましたが、低酸素血症の危険があるため近年は推奨されていません。少なくとも酸素投与を併用するなど、慎重なモニタリングが必要となります。抗不安薬や抗けいれん薬などの薬物療法も行われますが、同じく酸素飽和度(SpO2)モニタリング下で投与することが推奨されています。
過去に経験のある方は、過度の緊張や不安などが起きる状況をさけるように注意してください。またうつ病などの精神疾患や不安症、パニック障害などがある方は、それらに対する治療が発症防止に有用なことがあります。一般に予後は良好で、数時間で症状は改善します。
(2025年9月)