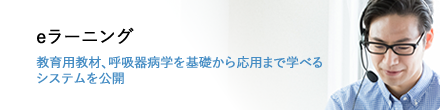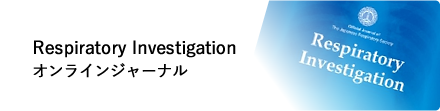呼吸器の病気
I.その他
気管支拡張症
きかんしかくちょうしょう
1)気管支拡張症について
気管支拡張症は、口から吸いこんだ空気を肺胞まで届ける気道(空気の通り道)である気管支が、損傷のために拡張したまま戻らない状態になる病気です。これにより、慢性的な咳・痰・呼吸困難といった症状を引き起こします。
気管支拡張症は一つの原因で起こる病気ではありません。さまざまな病気や体質、生活背景などが重なり合って起こるため、医学的には「症候群(しょうこうぐん)」と呼ばれています。「症候群」というのは、決まった一つの原因から生じる病気ではなく、いくつかの異なる原因によって似たような症状や体の変化が現れる状態のことを意味します。
気管支拡張症を合併する病気としては、感染症として、肺結核およびその後遺症、肺非結核性抗酸菌症、細菌性肺炎、新型コロナウイルス感染症、などがあげられます。気道の障害としては、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、びまん性汎細気管支炎、気管支喘息、アレルギー性気管支肺アスペルギルス症などで合併します。また、自己免疫性疾患である関節リウマチ、シェーグレン病や潰瘍性大腸炎でも気管支拡張症がしばしば合併します。その他に、稀な疾患ですが、原発性線毛機能不全症候群、低ガンマグロブリン血症などの免疫不全症、気管・気管支軟化症でも気管支拡張症を合併します。海外では嚢胞性線維症やα1アンチトリプシン欠損症も気管支拡張症を合併することがありますが、日本における患者さんの数は少ないです。
2)有病率について
日本の健康保険のデータを用いた検討によると、2021年度には人口10万人あたり86人程度がこの病気と診断されています (1)。このことから、国内には少なくとも10万人以上の患者さんがいると推定されます。
年齢が上がるにつれて有病率は増加し、男性より女性に多くみられることが特徴です。
3)病態と原因
気管支は、痰や細菌などの異物を体外へ排出する「気道クリアランス」という自浄作用を持っています。この機能が低下すると、気道内に痰や細菌が停滞しやすくなり、炎症が繰り返し発生します。炎症部位では、白血球の一種である好中球から放出される「タンパク分解酵素」が気管支壁を損傷し、構造を破壊します。気道クリアランスの低下、感染、炎症、構造破壊という悪循環が繰り返されることで、気管支拡張症が進行すると考えられています (2)。
4)主な症状
慢性的に生じる咳や、膿性の痰が主な症状ですが、痰がのどに絡むだけで、痰を吐き出せない方もいらっしゃいます。感染症を合併すると痰の色が黄色や緑色に変化することがあります。また、微熱を自覚されるかたもいらっしゃいます。進行すると息切れを伴うようになり、時に血痰、喀血が起こることがあります。
普段よりも、咳、痰、息苦しさ、体のだるさ、血痰などの症状が2日以上悪化し、追加の治療が必要になる状態は「増悪(ぞうあく)」と呼ばれます。
5)診断と評価
診断は、胸部CT検査で拡張した気管支を確認し、さらに、慢性の咳や痰、増悪の既往といった臨床症状を合わせて行います。
病状の程度を明らかにするために、炎症・免疫状態を調べる血液・生化学検査、肺活量や1秒量などを測定する肺機能検査を行います。また、痰の中に含まれる細菌を特定するための喀痰検査や、気管支内部の観察が必要な場合は気管支内視鏡検査を行います。
血痰や喀血が続く場合、どこから出血しているのかを探すため、造影剤を用いたCT撮影、気管支鏡検査、血管造影検査を行います。
6)治療法
気管支拡張症の原因となる病気が特定されている場合、その病気の治療を行います。
慢性的な痰の排出を促すために、気道クリアランス療法を行います。これには、深呼吸や咳・ハッフィングを組み合わせたアクティブサイクル呼吸法、器具を用いて行う振動呼気陽圧療法、体位ドレナージなどがあります。また、去痰薬の内服、生理食塩水の吸入を行うことがあります。
増悪時には抗菌薬での治療を行い、増悪を繰り返す場合はマクロライド系抗菌薬を少量持続的に内服することがあります。
新たな治療薬として、好中球のタンパク分解酵素を抑えるDPP-1阻害薬が、将来的に使用可能になる見込みです。増悪頻度を減らし、呼吸機能の悪化を抑制する効果があります (3)。
体重・筋肉を減らさないように、栄養療法、リハビリテーションを行います。進行し低酸素状態になられた際には、酸素吸入を行います。
合併症として喀血を繰り返す場合には、血管カテーテルを用いた塞栓術などで止血を試みます。また、病変が肺の一部に限局している場合には、手術による切除も選択肢となります。
7)生活上の注意点
- 禁煙:喫煙は気道クリアランスを低下し、呼吸機能を悪化するため、禁煙が不可欠です。
- 感染対策:風邪やインフルエンザなどの感染症は増悪の引き金となります。手洗いやうがい、適切なマスク着用、ワクチン接種などを徹底しましょう。
- 増悪時の対応:普段と異なる症状が現れた場合は、速やかにかかりつけ医に相談し、適切な治療を受けてください。
8)予後について
気管支拡張症重症度分類(Bronchiectasis Severity Index: BSI)では、年齢、体重、呼吸機能、過去2年間の入院、前年度の増悪頻度、喀痰中の細菌の検出、呼吸困難、肺内での病気の広がりなど9つの項目で重症度を評価します。重症度が高いほど、入院頻度が高くなる、あるいは予後が不良となることが示されています (4)。適切な管理と治療により、症状をコントロールし、生活の質を維持することが重要です。
参考文献
- Asakura T, Wang P, Mohanty M, Nagamuthu C, Tang F, Simeone J, et al. Incidence and Prevalence of Non-cystic Fibrosis Bronchiectasis in Japan. American Thoracic Society International Conference Meetings Abstracts. 2024 May ;A3173-A3173.
- Shteinberg M, Waterer G, Chotirmall SH. A Global Effort to Stop the Vicious Vortex: A Special American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Issue for World Bronchiectasis Day 2024. Am J Respir Crit Care Med [Internet]. 2024 Jul 1;210(1):1-3.
- Chalmers JD, Burgel PR, Daley CL, De Soyza A, Haworth CS, Mauger D, et al. Phase 3 Trial of the DPP-1 Inhibitor Brensocatib in Bronchiectasis. N Engl J Med. 2025 Apr 24;392(16):1569-81.
- Chalmers JD, Goeminne P, Aliberti S, McDonnell MJ, Lonni S, Davidson J, et al. The bronchiectasis severity index. An international derivation and validation study. Am J Respir Crit Care Med. 2014 Mar 1;189(5):576-85.
(2025年9月)