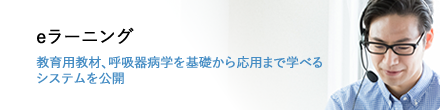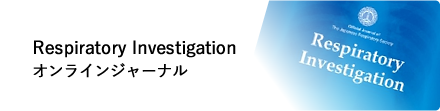呼吸器の病気
D. 間質性肺疾患
肺胞蛋白症
はいほうたんぱくしょう
病気の概要
肺の中には、数億個の肺胞という袋があります。肺胞は毛細血管との間で、酸素と二酸化炭素を交換します(呼吸)。肺胞内には、肺胞が潰れないよう表面張力を適切に保つサーファクタントというタンパクが存在し、その量を肺胞マクロファージが調整します。肺胞マクロファージの異常によりサーファクタントを含む老廃物が肺胞内に過剰に貯留した状態が肺胞蛋白症です(図A)。自己免疫性、続発性、先天性/遺伝性、未分類(原因不明)に分類され、成人患者の9割が自己免疫性です。
疫学
新潟大学の研究者が2019年に報告した自己免疫肺胞蛋白症の疫学調査では、1年間の発症率は100万人あたり1.65人、罹患率は100万人あたり26.6人でした。診断時の年齢中央値は51歳、男女比は2:1、喫煙率が56%でした。地域差はないと考えられています。
発病のメカニズムなど
自己免疫性は、マクロファージの成熟を促すGM-CSFという物質の働きを阻害する自己抗体(抗GM-CSF抗体)が誘導されることで発症します。一部に塵芥のばく露が原因と推測されています。続発性は血液疾患、感染症、膠原病などに合併します。先天性/遺伝性はGM-CSF受容体の異常が報告されています。
症状
主な症状は労作時呼吸困難です。その他に咳、喀痰、体重減少、発熱などがあります。無症状の場合があり、健診等で偶然発見されることがあります。
診断
胸部CTで肺胞蛋白症を疑い、気管支鏡検査で採取した気管支肺胞洗浄液の性状や病理組織を確認することにより肺胞蛋白症であることを診断します。自己免疫性は、血清のGM-CSF抗体陽性により診断します。続発性は抗体陰性と原疾患の存在、遺伝性の場合は遺伝子変異を確認することにより診断します。
治療
軽症の場合は無治療で経過観察することがあります。自己免疫性の場合はGM-CSF吸入療法を行います(図B)。重症の場合は全身麻酔下に肺洗浄(全肺洗浄)を行います。内科的治療が奏効しない場合は肺移植を検討することがあります。
生活上の注意
肺胞マクロファージの機能低下のため、感染症に注意します。また、禁煙することが望ましいです。
予後
自己免疫性の場合の5年生存率は96%、11年生存率は86.6%と良好ですが、合併する肺線維症合併例は難治性です。続発性、先天性/遺伝性の場合は予後不良です。
詳しい情報については、下記サイトをご参照ください。
https://pap-net.jp/ 日本肺胞蛋白症患者会
https://gipo.or.jp/ja/pap/illness/ GM-CSF吸入推進機構
(2025年9月)
図A、図B