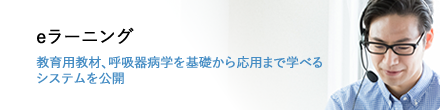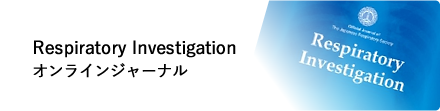呼吸器の病気
A. 感染性呼吸器疾患
インフルエンザ
いんふるえんざ
概念
インフルエンザは、一般的な風邪とは異なり重症化しやすく、日本国内では毎年12月~3月に流行することが多いです。
疫学
インフルエンザウイルスにはA型、B型、C型などの種類がありますが、ヒトで流行を引き起こすのは主にA型とB型です。潜伏期間は通常1~4日間(平均2日間)です。
発症のメカニズム
人から人に感染し、感染した人がせきやくしゃみで空中に吐き出した分泌物に混じったウイルスが、他の人に接触して口や鼻から侵入することによって感染が成立します。
症状
突然の発熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛などが現れ、咳、鼻汁、咽頭痛などの気道症状がこれに続き、約1週間で軽快します。主な合併症として高齢者では肺炎と小児では脳症が重要です。
診断
流行状況、患者との接触歴の確認、典型的な臨床症状が診断の第一歩となります。インフルエンザ迅速診断キットにより短時間で簡便に診断でき、A型とB型の鑑別も可能です。
治療
①対症療法
基礎疾患のない若年者は消炎鎮痛剤などの対症療法で自然に軽快します。
②抗インフルエンザ薬
高齢者や基礎疾患のある患者さんには抗ウイルス薬が推奨されています(表1)。発症後48時間以内に使用しなければ、効果は低下するため、早めの服用が勧められます。
生活上の注意
①一般的な予防方法
マスクの着用、手洗いの励行によりウイルスの体内への接触や侵入を減らすことが可能です。
②インフルエンザワクチン
インフルエンザワクチンは不活化ワクチンのため、免疫のない患者に接種しても感染を起こす心配はありません。高齢者、基礎疾患のある患者、医療従事者などはワクチン接種をすることが推奨されています。
③抗インフルエンザ薬による予防
インフルエンザの症状が重症化しやすい人(インフルエンザ患者と同居している人や共同生活をしている人で、65歳以上、呼吸器または心臓に慢性的な疾患がある人、糖尿病などの代謝性疾患がある人、腎機能障害のある人)に対しては、抗インフルエンザ薬を使用した予防投与を行うこともあります。
予後
発症早期に抗インフルエンザ薬を投与すれば、予後は比較的良好です。
(2025年8月)
表1 国内で使用可能な抗インフルエンザウイルス薬
| 商品名 | 作用機序 | 有効な型 | 投与経路 |
|---|---|---|---|
| リレンザ® (ザナミビル) |
ノイラミニダーゼ阻害 | A型とB型 | 吸入(1回10mg、1日2回、5日間) |
| タミフル® (オセルタミビル) |
経口(1日1カプセル、2回、5日間) | ||
| ラピアクタ® (ぺラミビル) |
点滴静注(1回300mg、単回) | ||
| イナビル® (ラニナミビル) |
吸入(1回40mg(10歳以上)、1回20mg(10歳未満)、単回) | ||
| ゾフルーザ® (バロキサビル) |
キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害 | 経口(1回10mg(12歳未満の小児で体重10kg以上20kg未満)、1回20mg(12歳未満の小児で体重20kg以上40kg未満)、1回40mg(12歳未満の小児で体重40kg以上、成人及び12歳以上の小児で体重80kg未満)、単回) |