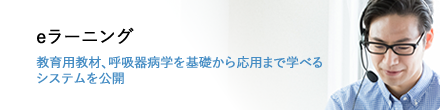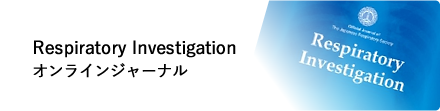活動・取り組み
日本呼吸器学会 海外学会参加助成 被助成者一覧
ATS 2025 参加報告書
国立病院機構東京病院
加藤 貴史
国立病院機構東京病院 呼吸器内科・臨床研究部の加藤貴史と申します。この度、日本呼吸器学会より、米国サンフランシスコで開催されたATS 2025 International Conferenceへの参加助成をいただき、同学会へ参加させていただきました。
私の発表演題は、「Identification of MUC5B-expressing Alveolar Type 2 Cells in Subjects With and Without Lung Disease」で、通常はMUC5Bを発現していないとされる2型肺胞上皮細胞に、MUC5Bを高度に発現している個体があること、またその現象が、特発性肺線維症の発症リスクであるMUC5B遺伝子のプロモータ領域の遺伝子多型に関連することなどを報告しました。ILDに関する基礎研究が並ぶPoster Discussionのセッションでの発表で、重厚な研究発表が多くある中、私の演題はやや軽めの内容でしたが、それでも多くの方から質問やご意見をいただきました。かなり突っ込んだ質問をしてくる方もおり、もしかしたら投稿中の論文のレビュアーなのではないか、などと勘繰りながら、議論をさせていただきました。今後の研究の発展につながりそうな内容もあり、大変励みになりました。
日本呼吸器学会などの国内学会でも、多くの研究成果に触れたり、他施設の先生方と交流したりできますが、ATSは世界中の国からの参加者がいることに加え、臨床医だけでなく、基礎研究者、看護師、理学療法士、企業職員など、幅広い職種の専門家が一堂に会する、お祭りのような面もあります。例えば呼吸リハのセッションや、企業の出展ブースを見てみることなどでも、自身の視野を広げたり、日々の臨床に生かせる情報を得たりすることができると思います。個人的には、院内で携わっている新規薬剤の治験のグローバル統括者の方と面会して、治験の組み入れ条件や今後の治験の見通しなどについて議論できたことも、貴重な経験になりました。
Conferenceの会期中(日曜午前から水曜昼まで)は、フルで学会に参加しましたが、夕方以降は、アメリカや日本の大学の研究者の方と会食をしたり、かつての同僚の先生と交流をしたり、学会終了後にアルカトラズ島の観光ツアーに参加したりなど、非常に有意義な、また非日常的な経験をすることができました。
今回は、今年3月に当院で後期研修を終え、引き続き常勤医として勤務している若手の先生も一緒にATSに参加しました。彼は初めての国際学会参加でPoster Discussionでの発表となり、かなり緊張した様子でしたが、終わってみれば良い経験で、今後の臨床・研究活動へのモチベーションが高まった様子が見て取れました。
今後参加を考えている若手の先生方へのメッセージですが、海外学会に参加する障壁として多くあるのが、① 英語に自信がない ② 研究内容に自信がない ③ お金がない という点ではないかと思います。それぞれの点について、私の考えや対処法を以下に述べます。
① 英語に自信がない → ポスター発表でもポスターディスカッションでも、自分の研究内容に興味を持ってくれる人は、たとえ英語がよくわからなくても、わかりやすい言葉で置き換えてくれたり、ゆっくり話してくれたりします。その先生も、研究内容をよく知りたい、と思って質問をしてくれているからです。もっと英語ができるようになってから参加したい、という人もいると思いますが、日本で忙しい臨床や研究業務を行いながら、次の年に英語力が高まっている人などはほぼいないでしょうし、国際学会での発表で、どのようなスキルが必要かは、実際に参加してみないと分からないことも多いと思いますので、国際学会で使える英語とはどういうものなのか、を体感するためにも、まずは思い切って参加してみるのがよいと思います。
② 研究内容に自信がない → ATSには、臨床研究や基礎研究以外に、症例報告のポスターセッションも多くあります。特に希少性があるわけでも、教育的なわけでもなさそうに見える発表も山ほどあります。日本には、呼吸器の若手医師が学会発表する場として、呼吸器学会地方会や内科学会地方会、各学会の年次集会など、多くの機会が用意されていますが、アメリカでは、ATSがレジデントや後期研修医にとっての症例発表の場になっているようです。日本で、Case reportとして今後投稿しようかと考えている症例がある、という程度でも、ATSに参加するには十分だと思いますので、まずは一度参加してみて、さらに意欲が高まる、ということなら、さらに高いレベルの研究を行って、翌年以降に改めてトライする、というくらいの感覚でよいと思います。
③ お金がない → これは気の持ちようではどうにもならない問題ですので、呼吸器学会の参加助成や、各病院や医局の補助制度を可能な限り活用するしかありません。それぞれの病院や診療科で、若手の先生の海外学会参加に充てることができる研究費がある場合もあります。運よく、良いメンター(スポンサー)を見つけられれば、サポートをしてくれるかもしれません。皆様の幸運を祈ります。
繰り返しになりますが、海外学会への参加により、日常とは異なる経験や刺激を得ることができます。私は過去に米国の研究機関で勤務していたこともあり、ATSに参加して、海外の研究者とのコネクションを維持・発展させていきたいと考えておりましたが、今後も参加を続けたい、また若手の先生方へも働きかけを続けていこう、と改めて強く感じました。
最後に、この度、海外学会への参加助成をしていただきました日本呼吸器学会、事務局の皆様、先生方に心より御礼申し上げます。私自身も、同世代の先生も、また若手の先生も、積極的に海外学会に参加したい、と思える環境が作れるよう、日々の臨床・研究に精進したい、と感じるATS 2025でした。