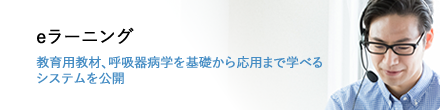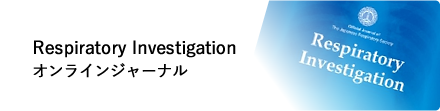404 Page not found
お探しのページは見つかりませんでした。

2022年3月31日より、
一般社団法人日本呼吸器学会ホームページを大幅にリニューアルいたしました。
リニューアルにともない、ページやファイルのURLが変更になっておりますのでご注意ください。
お探しのページは、移動または削除された可能性があります。
お手数ですが、トップページから再度アクセスしてください。
このページをブックマークに登録されていた方は、
お手数ですがブックマークの更新をお願いいたします。
The page you’re looking for can’t be found.
Please click here to go to the site top.
If you bookmarked this page, please update.